今回は2022年7月13日、『真夏の絶恐映像 日本で一番コワい夜』に登場する笹原留似子さんをご紹介します。
ネット上でも多くの方が笹原留似子さんの「おもかげ復元師」の活動をブログで紹介されてますね!
ぼくも今回はじめて笹原留似子さんや納棺師という仕事について調べてみました。
納棺師ってなに?
納棺師とはなんとなくわかりそうで詳しくは知らないという職業ではないでしょうか。
2008年に放映された、本木雅弘さん主演映画「おくりびと」はご存知ですか?
元チェロ奏者の男が納棺師見習いとして再就職し、納棺師=おくりびととして成長していく物語が話題を呼びました。
その映画を通じて納棺師という職業を知ったという方も少なくないでしょう。
この記事の主な内容
番組では「コワい」というキーワードで、笹原さん不思議な体験談が取り上げられるようですが、
この記事では納棺師の中でも異能と言われる笹原さんについて
・笹原さんのPROFILE
・納棺師というお仕事
・笹原留似子さんの異能
・「おもかげ復元師」を知るべき理由
という内容を紹介していきます。
この記事から伝えたいこと
悲しい出来事に寄り添い、残された人たちが前に進めるよう手を差し伸べる仕事。
けっして楽ではない納棺師という職業や、その職業で「復元師」というあらたなスタイルを確立している笹原さんについて知ることで
『人の役に立つために本当に必要なことはなんなのか』
そういったことに気づくきっかけとなるはずです。
「今、自分の生き方に悩みや迷いがある。」
そんな方にこそ、この記事を読んだあとなら「いまを生きるジブン」と「おなじように生きている他の誰か」に今よりもう少し優しくなった自分に出会えるでしょう。
笹原留似子さんの「おもかげ復元師」という仕事を知ってよかった、ときっと思ってもらえるはずです。
それでは参りましょう!
笹原さんのPROFILE

【PROFILE】 笹原 留似子(ささはら るいこ) ・株式会社 桜 代表取締役 ・復元納棺師・おもかげ復元師 札幌市出身、岩手県北上市在住。 北海道神宮に正規の巫女として奉職。 死やいのちに関わる民俗学の語り部としてYouTube「おもかげチャンネル」を配信。 2007年、『株式会社 桜』を設立。 セミナー講師として医療従事者、介護職、宗教者、葬儀業者などに年間100件を超えるセミナーを行っている。 東日本大震災では遺族や機関関係者から呼ばれ遺体安置所をまわり、5ヶ月で300人を超える「復元ボランティア」として奔走。 その活動はNHKスペシャル~最期の笑顔~で紹介される。 現在も震災遺族の会「いのち新聞」の代表として震災遺族の支援を続けている。
そのほか、2015年には社会貢献支援財団より、社会貢献賞受賞。2019年に警察署協議会委員を拝命されています。
山伏の祖父を持ち、自身も巫女として命やスピリチュアルな背景に繋がりをもつ笹原さん。
もちろん、霊能者であるとかお祓いができるとかという類の方ではありません。
故人とその家族と寄り添い、共感する。
これまで1万人以上の人生の終わり、そして旅立ちに立ち会ってきた日本屈指の「納棺師」、それが笹原留似子さんです。
そんな笹原さんが「復元師」と言われるようになったのは、実は故人のご家族につけて頂いたことがキッカケだったそうです。
笹原さんが故人のお顔に刻まれたシワに指を沿ってなでていると、段々と緊張が取れ、こわばった表情が優しくなっていくそうです。
笹原さんは納棺の時間に、事故や病気でなくなられた故人に対して
「もっとなにかしてあげられたんじゃないか」
そのように心残りをもっているご遺族に、このようにお話するそうです。
「誰も悪くない。その人がいてくれたからこそ、これまでの楽しかった時間があり、今があるのです。故人も同じ思いではないですか」と。
笹原さんの人柄には、庭に咲く一本の桜のように、そこで暮らした家族(人生)を見守ってくれているような、包み込む優しさを感じます。
ご自身の会社の社名も「さくら」。笹原さんらしいお名前ですよね♪。、
納棺師という仕事
映画『おくりびと』で広く知られるようになった、故人の旅立ちを手伝う仕事、それが納棺師です。
納棺師の仕事は故人のご遺体を棺に納めること。しかし、ひとことに「納棺」といっても、そこにはやはり様々な手順や技術、知識が必要となります。
たとえば、活動を停止した肉体は自然放置では確実に朽ち果てていきます。
そのため防腐液で腐敗を抑えたり、死化粧や死装束を着せたりなど綺麗な状態になるようにご遺体の管理も行います。また、湯灌(お体を清潔に清めること)も納棺師の仕事のひとつです。
葬儀社から依頼が入ると、納棺師が火葬まで一貫してご遺体の状態を管理します。
ちなみに、納棺師は「湯灌師」や「おくりびと」などとも呼ばれており、職業に関する呼び方は厳密には決まっていません。
お通夜から葬儀、火葬まで2〜3日から1週間ほどかかることもあるでしょう。
一つ一つの手仕事に思いをこめ、丁寧に行う納棺師のお仕事は唯一無二のお体を預かる職業です。
やり直しももちろん効かないですし、ご遺族にとって本当に大切なひとときを預かり、ご一緒する大変な職業です。
さらに故人のおなくなり方しだいでは、状態として完全であったりキレイであることばかりではないでしょう。
場合によっては、ぼくたちでは目を背けてしまうような状態もないとは言えません。
それでも、いつも変わらず大切にお預かりし、キレイにお体をきよめ、防腐処置をほどこし、最後のご挨拶ができるようお化粧をする。
こうやって書くのは容易いですが、実際のお仕事は精神力もタフでないと続けられない職業だと思います。
納棺師は1954年の青函連絡船洞爺丸沈没事故から生まれた職業
納棺師が誕生したのは1954年の青函連絡船洞爺丸沈没事故からでした。
葬儀は古代から続いており、非常に長い歴史がありますが、納棺師の歴史は100年に及びません。
1954年に起きた青函連絡船洞爺丸沈没事故当時、北海道函館市の海岸には多くのご遺体が流れ着きました。
流れ着いたご遺体を遺族へ引き渡す作業を、葬儀業者が地元の住民に依頼したことをきっかけで納棺師という商業がスタートします。
納棺師は葬儀業者の下請けとして名乗り始めた造語なので、仏教や伝統文化と直接的な関連性はありません。
あくまでも私見ですが、歴史的背景からみると、納棺師の始まりは決して尊敬された職業ではなく、むしろ低所得層や貧困層のかたが行う「隠された仕事」だったかもしれません。
しかし、それから約60年たち「納棺師」という職業は「おくりびと」とも呼ばれ、葬儀には欠かせないだけでなく、
ご家族のこころのケアまで届く仕事となりました。
そこには「どうすれば故人とご家族にとって最高の旅立ちになるか」を考え続けてきた歴代の納棺師の方々の「思いやる仕事」が実を結んでいるのでしょう。
そうして紡がれた伝統や技術が笹原さんという類まれ無い「納棺師」の出現によって昇華され、「おもかげ復元師」というあらたなスタイルを誕生させます。
笹原留似子さんの異能

笹原留似子さんは、納棺師の中でも異能をもつと話題です。
「復元納棺師」として故人と遺族に寄り添ってきた笹原さん。
「復元」とは交通事故や災害などで亡くなった故人の生前のおもかげを探し、できる限り元の状態に戻す技術のことだそうです。
復元という技術をもつきっかけとなったのは、14年前にであったご遺体とご家族の絆でした。
笹原さんが「復元」ということを始めたきっかけ
14年前、笹原さんが依頼を受け、納棺師としてあるお宅に駆けつけます。
そこには「お父さんに会いたい。お父さんは帰ってくる」と泣く子供たちがいました。
父親を事故で亡くしたのです。
棺(ひつぎ)に入れられたご遺体は損傷が激しいため、葬儀社や親御さんの判断で子供たちは父親と対面させてもらえませんでした。しかし、子供たちは父親が帰ってくることを信じています。
「この子達になんとか会わせてあげたい」。
笹原さんはその思いではじめての「復元」処置に取り掛かかったそうです。
苦悶(くもん)の表情を浮かべた故人の姿を目にし、大好きだったあの人かどうかも分からない。
「こんなのお父さんじゃない」「誰か元に戻して」「もう一度だけ会いたい」
・・・そんな遺族の声に突き動かされ、これまで復元を続けてきたという笹原さん。
以下は納棺師、そして「復元師」としての笹原さんの言葉です。
変わり果てた姿のままでは、家族は悲しみと動揺から故人としっかり向き合えません。しかし、復元することによって、目の前の死を受け入れることができるようになります。
https://shimbun.kosei-shuppan.co.jpより引用
故人の声なき声をきくチカラ
そんな笹原さんは、たびたび警察から捜査に意見を求められることがあるそうです。
それは笹原さんがほかの納棺師とはちがい、ある特殊な能力があるからです。
それが笹原さんの異能、「声なき声をきくチカラ」です。
実際に声がきこえるという心霊的なものではないようですが、笹原さんはご遺体に触れるだけで様々な情報を「きく」ことができると言います。
2019年に警察署協議会委員を拝命されたのも、そういった活動からでしょう。
「おもかげ復元師」を知るべき理由
ここで、笹原さんの一冊の書籍をご紹介させていただきます。
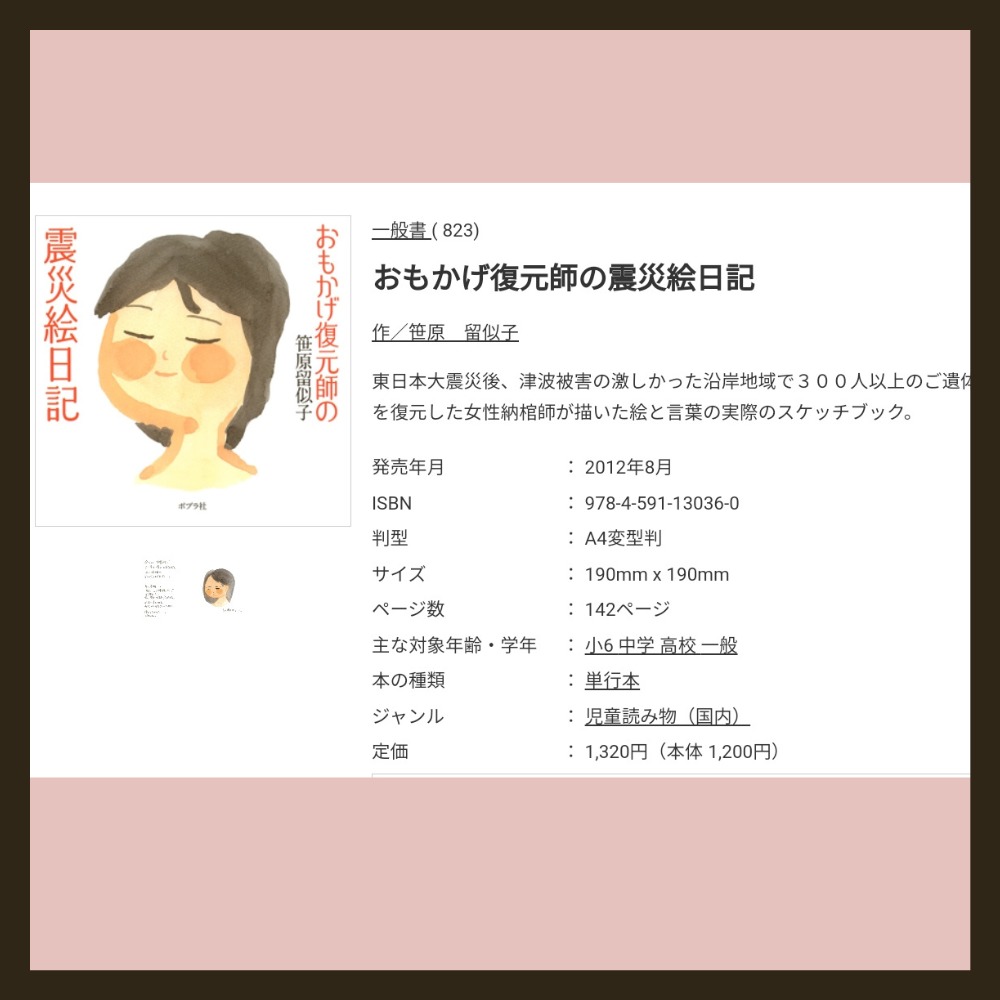
こちらは東日本大震災で300体以上ものご遺体に関わった笹原さんの記録です。 このとき、あるこどものご遺体に対して法的な関係で「復元」が出来なかった・・・ そのことが悔しくて、かなしくて。 一番初めにそのときに書いた書記が掲載されています。 わたしたちはあのとき、こういった方々の葛藤や苦悩、ご家族を津波で失ったかたに一番寄り添っていた人たちの姿。 それは決して忘れてはならないのです。
この本を通して復元納棺師として話題となり、NHKのスペシャル番組で取り上げられました。
「わたしはこの本を涙なしではみれなかった」
「日本人として(震災に対して)読むべき本がわからなかったが・・この本こそ、その本だ」
twitterでもこのようなコメントが多数投稿されています。#おもかげ復元師
こどもを失い、悲しみにくれ、なぜ助けられなかったのかとくやむ母親。
そういった姿を前にして、笹原さんはこのように伝えたい、そう語ります。
『自分を責めるということは相手を深く思っている証し。愛しているから、大切だからこそ湧いてくる苦しい気持ちを大事にしてほしい。』
『後悔や自責の念もひっくるめて自分と相手の関係性を見つめ直すことが、再び立ち上がり、前進する力につながるのです。』
わたしたちは生きている以上、いつかは大切なヒトをなくしたり、大切な何かをうしなうことがあるでしょう。
そんなときに、こういった本が傍らにあれば、ほんとうの意味でこころを助けてくれる。
震災はとてもたくさんの悲しみを生みました。
しかしその分だけ、悲しみを乗り越える勇気が生まれた震災でもあります。
もしよければ、この本の中にあるエピソードから勇気を分けてもらってはいかがでしょうか。
学びまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はどんなひとにも必ず訪れる人生の悲しい場面に、故人と家族の絆をつむぎ、あらたな旅立ちをお手伝いする「納棺師」、
そしてその中での故人の声をきき、おもかげを復元する類まれ無い技術を持つ
笹原留似子さんについて紹介させていただきました。
おもかげとは「面影」と書きます。
本当の表情は「面(オモテ)」の「影」にある。
それは深く深く刻まれたシワの影かもしれません。
あなたの横にいる大切なヒトと長く年を重ねて、そのおもかげをしっかり焼き付けておくことが
もしかしたら「しあわせ」という意味なのかもしれませんね。
シワが増えたら、その分だけ喜びが増えている証拠です。
それではまた!
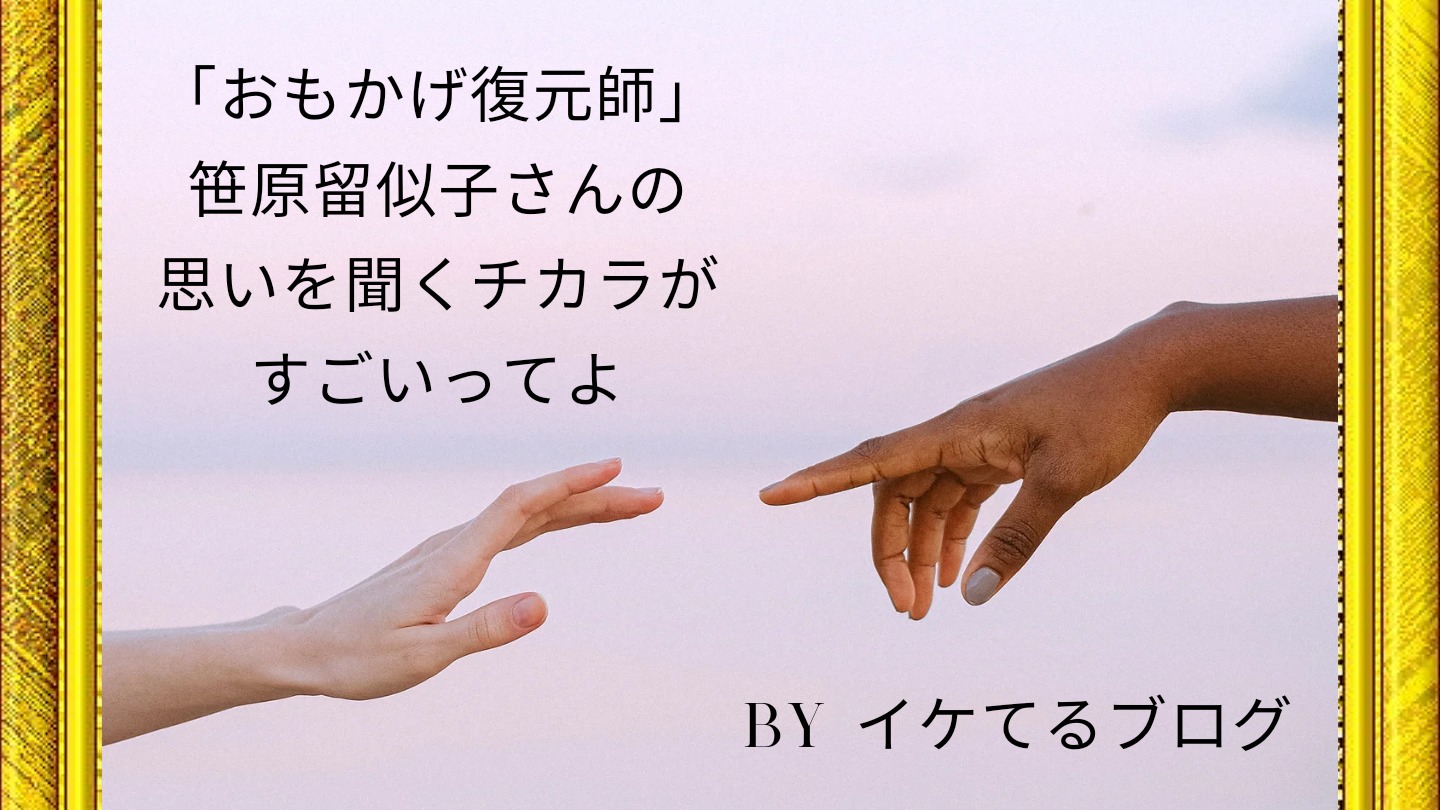


コメント